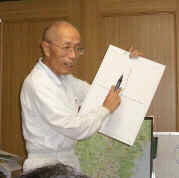
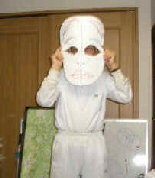

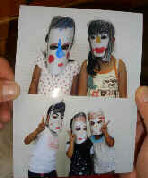
QOPODOVáïñ@VPSúi j
QÁÒ@iàVæ¶A¬o³ñA¯q³ñA´G³ñAûü´\³ñA
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Oì³ñAÉ¡T³ñA~c³ñA²¡ü³ñAÁ¡
u|[gvEbè
u¨Êðìév@ccccccccccccccccccccccccccccccccc@iàV
È ßì¬íAvRbvÌvoy_gAQW{^Æ@ccccccccccc@¯q
ÅñÕñÌöÆuHרÌÁ»vA@ÔR©RÌÆÌuXYo`ÌW{v@cccccccc@Á¡
TC_[ìè@ccccccccccccccccccccccccccccccccc@ûü´\
©R©(»ÎÒ) QOPO@cccccccccccccccccccccccccccc@É¡T
w±ÄUNu®¨Ì©ç¾Ìͽç«v@ÄzAÁ»@ccccccccccccccccc@´
@
áïÅÐî³ê½àÌ@ÈÇÈÇ
¨Êðìé@iiàVj
@xJ¬Ìö¯ÙÌúÛãqÇ೺ÅÌÀHÅ·B
@iàVæ¶ÍAö¯ÙÌúÛãqÇ೺ÅNɽxàA¢ë¢ëÈàÌÃè®ðsÁĢܷªA¡ñͨÊìèÅ·B
@HìpûáðgÁÄAq½¿ÉAå«Ä_Ci~bNȨÊðìç¹Üµ½B
@çð`©¹éÆ«AûáÌüðpµÄA\Ìüðܸ«Ü·B
@»Ìüð½æèÉAÚâ@ð©¹Ä¢«Ü·B
@íµ¢w±Ì¬êÍA|[gðQƵľ³¢B
@¨Êð¯½q½¿ÍAÆÄàyµ»¤Å·ËB@
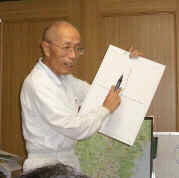
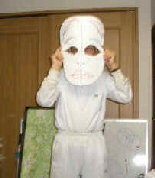

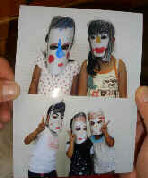
@
@
@NXÌCxgâÈwNuÈÇÅÈPÉÈ ßðìé±ÆªÅ«Ü·B
@È ßì¬íðܸìèÜ·BìèûàÈPÅ·B
@WÌ¢½ù¿
ÌA~ÌÊÌWÌ^ñÉAçʵÈÇÅðJ¯Ü·B
A5cmç¢Ì·³Ì{gðWÉæèt¯AibgÅÅèµÜ·B
@({gÆibgÍZbgÅz[Z^[ÉÁĢܷB{gÌaÍA3mmç¢)@
BA~ÊÌ{ÌÉÉÍAºÌûÉæeÅðū龯½³ñJ¯Ü·B
C100~VbvÈÇÅnfB^CvÌî@ðwüµAHðÆÁÄ[^[̲ÆWɯ½{gðAÞè¹ïÌSÇÅÂȬܷB
@±êÅAÈ ßì¬íÍ®¬B
@ ÆÍA^ñÌÊ^Ìæ¤ÉAôÊíÆÄñÕçK[hÅAÈ ßð©çßæé{bNXðìèÜ·B
@³ÄA¢æ¢æÈ ßðìèÜ·B
@ÊÉUÌ»ðXv[Pt®ç¢üêÄAWðµÄAAR[vâJZbgRÅÊÌêðMµÜ·B
AÊÌ¡Ì©çUÌöµÄ«½C̪oÄ«½çAM·éÌðâßÄÄñÕçK[hÌ{bNXÉڵܷB
Bî@Ì[^[ðñ]³¹éÆA©çöµ½UªoÄAâ¦ÄÈ ßÉÈèÜ·B
CÈ ßªoÈÈÁ½çAÊðoµÄAèεÅÈ ßð©çßæèÜ·B
@ÄÍÈ ßª·®É׽¢Äéæ¤Å·BìÁ½ç·®H×éÆæ¢Åµå¤B
@»ê©çAUàFt«Ìà̪ÁÄ¢éÌÅA»êðg¤Æ«ê¢ÈFt«ÌÈ ßªÅ«é»¤Å·B(EÌÊ^ÍÂFÌUðgpB)



@
@
vRbvÌuoy_g(KlR)@i¯qj
@upìèÍAq½¿ÉlCÌÈwVÑÅ·B
@X`[÷«ÌuRbvÍAI[vÅM·éÆkÞ«¿ª éÌÅA±êðg¤ÆÀ¿ÅupVѪūܷB
@§ÌÌRbvÌ`ªA½ÊÌ~¢`ÉkÞÌàsvcŨàµë¢Å·ËB
@¡ñÌñÄÌ~\ÍAñÉ|¯éRÉA100~VbvÅÁÄ¢½åÊÌuKlRvðgÁ½±ÆÅ·B
@½©Ég¦È¢©ÆAÈOA½³ñÁĨ¢½Æ̱ÆB
@r[Yà¯éÆA³çÉfGÈy_gÉÈèÜ·ËB
@


@
@
@
@
@
@
@
QW{^Æ»Ì@i¯qj
@{éÅàÈ©È©©çêÈÈÁÄ«½QW{^Å·ªA¯q³ñÌα·éìÀÌnæÉÍAܾܾz^ÌòÑð¤©RÌîiª©çêéæ¤Å·B
@ÌWµ½z^ðçµÄ¢½çAðYñ¾Æ̱ÆB
@EÌÊ^Ì©FÁÛ¢ÂÔÂÔªz^ÌÅ·B


@
@
TC_[ðìë¤@iûü´\j
@ÈÁīܵ½B
@ÈwNuÅTC_[ÃèðµÄA¿åÁÒè_âAJâÌ×ðµÈªçAyµAâ½Ä¨¢µ¢àÌÃèðµÜµå¤B
@Þ¿ÍA A»ANG_AdwAXA»µÄ( êÎ)TC_[ÌGbZXÅ·B
@ìèûàÈPÅ·B
@@P@Rbvɼª®ç¢
ðüêéB
@@Q@NG_Æ»ðÆ©·BNG_ÍC¬³¶Pt®ç¢B@»ÍCå³
¶Q tÈã
@@R@XðüêÄââ·B
@@S@d𬳶¼ª¢êéBñ_»YfÌAª¶·éB
@@T@ÅãÉCGbZXðQH®ç¢üêéB
@¨¢µ¢TC_[É·éÉÍA»ð½³ñn©³È¯êÎÈèܹñB
@sÌÌY_ù¿ÉàA½³ñÌ»ªn¯Ä¢éÌŵå¤ËB
@
@
¨à¿áXYo`ÌW{@iÁ¡j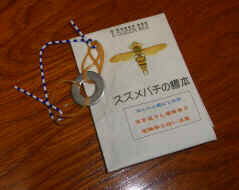
@ÔRÂN©RÌÆÉAhhÉqÇཿÆs«Üµ½B
@»±ÅA±ÌuXYo`ÌW{vÆ¢¤Alð¿åÁÆÁ©µÄyµÞS̨à¿áªu¢Ä èܵ½B
@±Ì³cÍuT\ÌW{vÆ¢¤àÌÅA¼àЩçs̳êÄ¢½æ¤Év¢Ü·B
@ÔR©RÌÆÌüÓÉÍn`àæ¢éÌÅAT\ªXYo`ÉÈÁ½Ìŵå¤ËB
@Ìd|¯ÍAå«ßÌNbvÆÖSQÂA5~Êç¢ÌbV[Å·B
@ éàÌìèÌ{ÉÍAÖSðÅè·éiðAúâûpbNðpµÄìÁÄ¢½Ì𩽱ƪ Á½ÌÅ·ªAEÌÊ^Ìæ¤ÉAå«ßÌNbvðg¤ÆÈPÉìêÜ·ËB
@
ÚÉßé@gbvldmtÖ
@@
QOPODOUáïñ@UXúi j
QÁÒ@iàVæ¶A¬o³ñA¯q³ñA~c³ñA´G³ñAÉ¡T³ñA
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@²¡^³ñAOì³ñA´ü³ñAÁ¡
u|[gvEbè
uÔEÀE½Ëv@AÜèů^ðÂéÉÍ@cccccccccccccccccccc@iàV
uV`E̽ܲAæ¤ÌÏ@vAÑÅæ¤ÌgÌÌÂèÌÏ@@cccccc@¯q
u¬ÈR[i[Auà¯âklµ¯ð©Â¯æ¤v@cccccccccccccccc@Á¡
u®¨Ì©ç¾ÌÂèÆ^®v@ccccccccccccccccccccccccc@ûü´G
{°YÎÅÎA¬c¬wZÈÊMuOúÆà¯vuQUúªHv@cccccccc@É¡T
w±ÄSNudCÌͽç«v@ccccccccccccccccccccccccc@ûü´ü
ªHÆf¯Ï@ï@cccccccccccccccccccccccccccc@Oì
@
áïÅÐî³ê½àÌ@ÈÇÈÇ
Üèů^@iiàVj
@µ[Ìúàßâīܵ½B
@iàVæ¶ÍAxJ̶NuÅÌw±ÌÅAÜèů^ðÜÁÄØèæé±Æ𳦽»¤Å·B
@êÂÌpÌðOªÉµÄÜéÆ¢¤Ìªïµ¢Æ̱Æŵ½B





@
ìØÌÔÅAÔ̵Ýð³¦æ¤@iiàVj
\\\\|[gæè\\\\
@@@@@¨ÉA¦Ä¢éìØÉA¢ÜÔÌç¢Ä¢éà̪ èÜ·B
@@@@@»ÌìØÌÔðÏ@µAðUµÄAÔªç¢Ä©çAÔÌíªÅ«éÜÅ̵ÝÉ¢Äl¦Ä¢«½¢B
@Æ¢¤±ÆÅAGhE¤ÌÔððUµÄÝܵ½B
@ªAÔÑçðæèÆAßµ×̪³ÍÀÉÈéªAq[Å·B
@bðØèJÆAíÌÔ¿áñªüÁĢܵ½B
@ܽAGhEÌÀàðUµÜ·B
@ÉÍíªÝ¢á¢ÉÈçñÅüÁĢܵ½B
@GhEÌâÌ·¶ÌƱëÉíªÂ¢Ä¢Ü·B
@±Ì·¶ªAíÉh{ªð^ñÅ¢éÌÅ·ËB



@
@
ÑÅAæ¤ÌgÌÌÂèÌÏ@@i¯qj
@RN¶Ì±ñÌç¿ûÌwKÅÍAV`EÌAIVðçÄÄAgÌ̵ÝðÏ@³¹Ü·B
@æ¤Ì©ç¾ÌÂèªAHרâ·Ý©É¤ÜK·éæ¤ÉÈÁÄ¢éÆ¢¤±ÆðÆ禳¹é±ÆªdvÅ·B
@ïÌIÉÍAêÂÉAûÌÂèÅ·B
@tðªÌOÅcɵÄH×éÌÉsÌ¢¢æ¤ÉAûͶEÉJæ¤ÉÈÁĢܷB
@»µÄAtð©¶éÌÅAûÌ`ÍÞ ²ªÂ¢Ä¢éûÉÈÁĢܷB
@
@ñÂÚÉA«ÌÂèÅ·B
@«Í½{ éŵ天BOÌûÉU{Ì«ª èÜ·B
@H×éÆ«ÉtÉ𨳦éAÍÜéÌÉsÌ¢¢AuÂß«vÉÈÁĢܷB
@ãëÌ«ÍW{B¨àµë¢±ÆÉ`ÍAu¢Ú«vÅ·B
@zÕÌæ¤È`ðµÄ¢ÄAt©ç¿È¢æ¤Éz¢Â¢ÄÆÜéÌÉÖÈ`Å·B
@®¨ðÏ@·éÌ_ƵÄA»ÌêŶ«ÄÌÉÇñÈsÌæ¢gÌÌÂèÉÈÁÄ¢é©AÆ¢¤±ÆªåØÅ·B
@¤ÜÅ«Ä¢égÌ̵ÝÉCñÆÅA»Ì®¨ÉàeµÝªí¢Ä«Ü·B
@³ÄA±ÌGßA¹HÈÇÅàAEÌæ¤ÈÊ^ÌѪæ©Â©èÜ·B
@¨»çAIVÌæ¤ÉÍD©êÈ¢æ¤Åµå¤ªAÈñÆAûâ«ÌÂèªæÏ@Å«Ü·B
@ÅàAÑÉGéÆh³êéÂ\«à éÌÅAÓªKvÅ·B
@¢©½©ÅßܦÄA§¾Èüê¨ÉüêÄÏ@·éÆ¢¢Åµå¤B
@¯Á±¤å^ȱÆà ÁÄAAIVæèÍ_ÅA±Ì̽ɶ«Ä¢épª©çêé±Æŵå¤B
@
@
{°YÎÅÎ@iÉ¡Tj
@åIªctßÉÍØèèâ´Aªc³êĢܷB
@Îp¬cå«ÈâÎÌÉAA±µÄRç¢ÌÎp¬ªÂóÉÁĢܷB
@´âÍ_«ÃDâÅ·B
@{°ÃDâÆvíêÜ·B
@»±ÉÎpªÌ½¢âΪAÂóÉÑüµÄ«Ä¢Ü·B
@ÂóÌÎpc´âªÃDâÈÌÅAͪµâ·¢ÌÅ·B
@Îp¬ÍAÙÚmEÅA»´ÌÔÉmEÌ»â
»Ì»ª©çêÜ·B
@mEcÎpi
»jÉ
ª»Éüè±Þ±ÆÉæÁÄASèªoÄ«Ü·B
@êÉÈéÌÅ·B
@ÎÅÎcg~Oðµâ·¢ÌÅA·®ÉÎÅÎÉ·é±ÆªÅ«Ü·B
@
ÚÉßé@gbvldmtÖ
@
QOPODOTáïñ@OTPQúi j
QÁÒ@iàVæ¶A¬o³ñAOì³ñAOY³ñA´³ñA´G³ñA
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¯q³ñA´ü³ñAÉ¡T³ñAÁ¡
u|[gvEbè
uVCÌ×v@ cccccccccccccccccccccccccccccccc@iàV
uàÌÌR¦û@UN@v@ccccccccccccccccccccccccccccc@´
àÌÃèEõÌؾ@ ccccccccccccccccccccccccccccc@¯q
@
áïÅÐî³ê½àÌ@ÈÇÈÇ
àÌÃèEõÌؾ@i¯qj
@¶ÍA~ØÁ½úðQgÝí¹½àÌÅA¼aÌP^RżpÉgܹĢܷB
@½¾±ê¾¯ÅAsvcÆX[YÉ]ªé¨à¿áÅ·B
@¼OÍí©èܹñB
@^ñÍuõÌؾvÅ·B
@TNÌÔ`Ìp`Å ¯½`«ÉÍAñÜiqªÍÁÄ èÜ·B
@½Î¤É௶æ¤ÉñÜiqªÍÁÄ é̼«ª ÁÄAõÌ éÙ¤Éü¯Ä`ÆAøFÉPÍlª©¦Ü·B
@Íóü@Ì¢çÈÈÁ½[ðØÁÄpµÄ¢Ü·B
@ÀãªèÅq½¿ÉìñÅà离¤ÈàÌÃèÅ·ËB
@


ÚÉßé@gbvldmtÖ
@
QOPODOSáïñ@OSQPúi j
QÁÒ@@@iàVæ¶A¯q³ñAÉ¡T³ñA´\³ñAOì³ñA´³ñAÁ¡
u|[gvEbè
ut̯E4Ìv@ cccccccccccccccccccccccccccccc@iàV
«»AuöC@ÖÔ̵Ýv»Ì2A©R©2010@cccccccccccccccc@É¡T
¯ÀÌC~l[V{bNX@ ccccccccccccccccccccccccc@Oì
áïÅÐî³ê½àÌ@ÈÇÈÇ
«»@iÉ¡Tj
@C
êÉàÈÁÄ¢éÄl̻ͫ»Å·B
@KXÌ_Å»ðËÆAL
bÆ¢¢¹ð§ÄÄAU®àKXÌüê¨É`íÁÄ«Ü·B
@oáÀÌ°÷¾Å»Ì±ð©ÄÝéÆAÙÆñÇ«ê¢È¢ÎpÅA嫳̻ëÁÄ¢éÛpÌæ꽱Šé±Æªª©èÜ·B


@
¯ÀÌC~l[V{bNX@iOìj
@Oì³ñÍAåäsV¶äÅAxÉ[NVbvðJ»¤Å·B
@»Ìàeª±Ìu¯ÀÌC~l[V{bNXvÅ·B
@©¹\ñ¯ÀªvgµÄ é³û`ÌJ[h©çD«È¯ÀðTIñÅA¯ÌɵsÌæeÈÇÅðJ¯Ü·B
@»êð§ûÌÉgݧÄÄA©çs[e[vÈÇÌõðʳȢe[vÅÆßÜ·B
@õ¹Í100~VbvÅÁÄ¢½C~l[VðªðµÄA»êÉgíêÄ¢½LED(FªÏ»·é)ðpµÜ·B@HìÆdCƯÀÆA¢ë¢ëwKÅ«éàÌÃèÅ·ËB@@


@
@
ÚÉßé@gbvldmtÖ
@